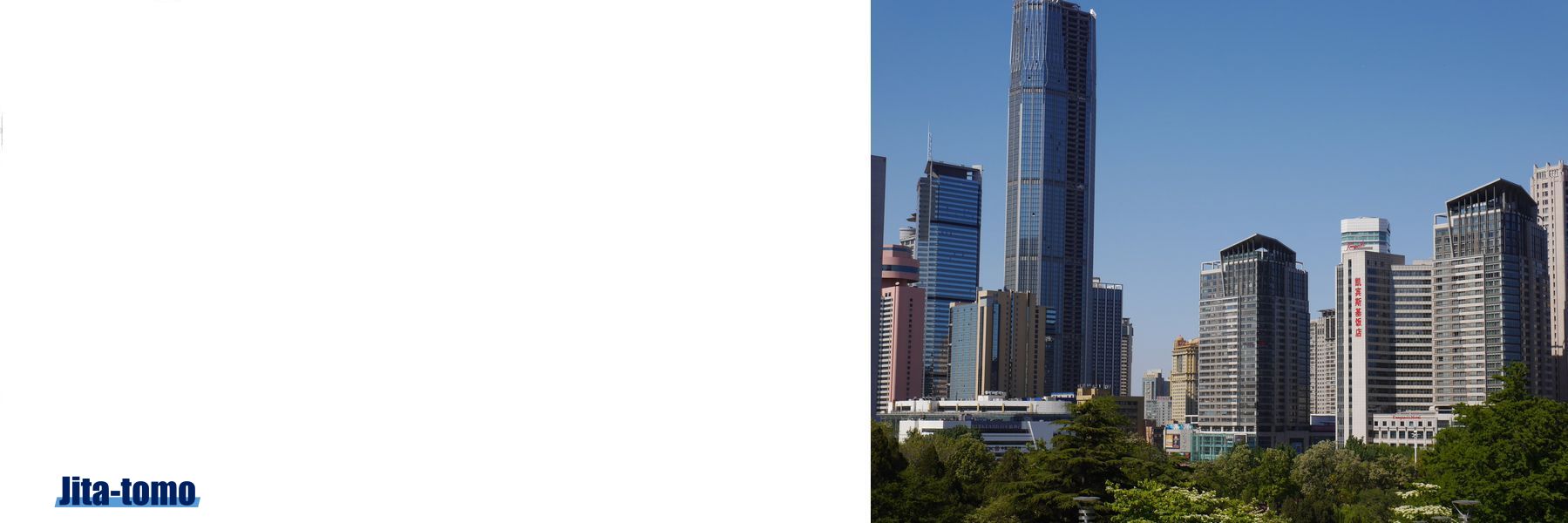如何にそっくりなものを作っても【画竜点睛】を欠いたなら…
「画竜点睛」は、最も重要なところ、肝心の部分が欠けている、との意。どんな事業でもマニュアルや製品はコピーができますが、文字や絵に現わし難い肝心なものがあるはずです。実は、そこが核心であり、軽んじていては中国で成功は危ういものになってしまいます。
中国の【良薬苦口】とのことわざ モノ申す社員の功用 イエスマンだけでは
「良薬は口に苦し」とは韓非子の言葉。意味は言うまでもない。心からの勧告や手厳しい批評などは、快くは聞くことは簡単ではない。しかし自分に足りないところや誤りを正すには良薬は非常に有利である。リーダーは「良薬」を飲み込む、度量と寛容を持たねばなりません。
【病は口より入り禍は口より出ず】 何気無いひと言が面倒のもとに
「禍は口より出ず」の原文は「病从口入,祸从口出(病は口より入り、禍は口より出ず)」。うっかり発した言葉が思いもかけない禍を招くことがある。不用意な発言はしないようにしたいもの。なかんずく、総経理(社長)という立場にある人は、自身の発言には十分注意しなければなりません。
【禍を転じて福と為す】 降りかかった禍を切り開くのは自身の積極性だ
「転禍為福」とは、禍や失敗があったときこそ、勇気を奮い起こし、強く明るく、前に踏み出すのがよい。突然、禍が頭上に降りかかり、御慌てることもあるであろうが、怯むことは不要だ。常に積極思考で努力を続けることが、福を引き寄せるきっかけにさえなる。
奮闘しても成果が出ない原因は何処に 【袖手傍観】が最も良くない
「袖手傍観」は、手をこまねいて何もせずにただ傍観する、ということ。任された会社組織の中で、「パワハラ上司」よりも良くない。傍観者然とした不作為のマネジャーは、社員達の活気を奪ってしまう存在になってしまう。
【臨時抱仏脚】では成功はできない コツコツと努力することの大切さ
「臨時抱仏脚」とは、言わば苦しい時の神頼み。普段努力をしないで,その期に及んでむやみに慌てること。それでは成功するわけがありません。日頃からコツコツと積み上げる、不断の努力こそが大切であると心得たいものです。根気強く励むことが成功をつかむ要諦。
【尾生之信】では成功は覚束ない 中国では臨機応変で臨むのが良い
「尾生之信」は荘子の残した言葉。頑なに約束を守り通し融通がきかないこと。真面目過ぎることの例え。グレーゾーン幅の広い中国では、むしろ臨機応変が役に立つ。そして、その采配を振るうことができるのは、妥当解がわかる総経理(社長)だけ…
【一敗地に塗れる】 論争して完膚無きまでの勝利を得るのは考えもの
「一敗地に塗れる」は史記にある言葉。中国語では「一败涂地」。一度の勝負で再起できないほどさんざんに負けること。負けられない論争であっても、常に相手のメンツをつぶさないような勝ち方をするのがよい。遺恨を残さない勝ち方を。
【人を治めて治まらずんば其の智に反れ】組織がうまく機能しない原因は自分にある
「人を治めて治まらずんば、其の智に反れ」とは孟子の言葉。組織がうまく機能していないようなときには、リーダー自身に知恵が足りず、やるべきことがなされていないのではないか、と考えて反省せよ、という厳しい箴言。
中国で【肝胆相照】の友人を持てば仕事が加速し人生も充実
「肝胆相照らす」とは、心底から打ち明けて親しく付き合うことを意味する、史記にある言葉です。このような友人の存在は、自身の仕事を加速、深化させる上で、大きな支えとなり、力となってもらえる。また、その付き合いは帰国後も続く、生涯の友人とも成りえます。