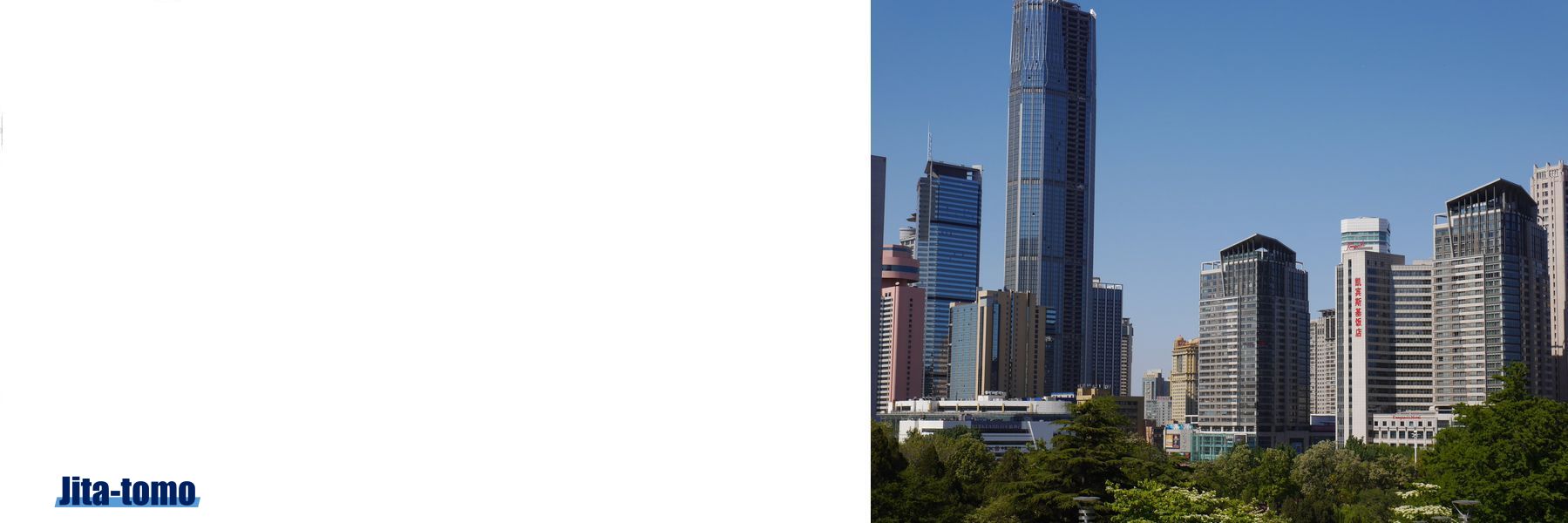【人と与にするには備わらんことを求めず】 只々感服 それ よく考えたものだ
「人と与にするには備わらんことを求めず」とは、相手の人に「完全」を期待してはならない、という書経の言葉。そもそも自分だって完全な人間ではないのだから。人には寛容がよい。そして感恩の心も。
【習慣 自然と成る】 毎朝のナマコ食は医食同源 変われば変わるものだ
「薬食同源」とは、薬と食物は起源が同じで、双方の間には明確な境界線はない、との言葉。。日本で言われている「医食同源」の語源。中国にはそういった食べ物や料理が豊富です。
【先ず隗より始めよ】よくできる社員の不思議 それを見て何を考える
「先ず隗より始めよ」とは」戦国策にある言葉で、何事も言い出した者から実行すべきである、或いは、遠大な計画も身近なことから始めよ、との意。リーダーたる者は、社員に要求するだけではなく、自らが先頭に立って実行すべきなのです。
例え【五里霧中】でも 一歩一歩着実に進めば見えてくる勝利の灯り
「五里霧中」とは、事情などがはっきりしない中、手探りで何かをすること。手掛かりがつかめず、方針や見込みが立たず困ったとしても、一歩一歩着実に事を運ぶことにより、やがては成功の二文字が見えてくる。
【騎虎之勢】ぬるま湯体質からの脱却 覚悟から成功は始まる
「騎虎の勢い」とは、一旦やり始めたら途中でやめることはできないことの例え。ぬるま湯に浸かる安逸な心に挑戦し、妥協せず覚悟を決めて事に当たるべきであり、そこから成功は始まる。
【鞭は長くとも及ぶこと莫れ】 中国ではアドバンテージを持つが故の危うさも
「鞭は長くとも及ぶこと莫れ」とは、長い鞭なのだが、いつも馬の腹には届かない、との意。つまるところは、力量不足であること。そこを補うのが総経理(社長)としてのナレッジマネジメントと、謙虚な心であろう。
【色 人を迷わさず 人自ら迷う】 中秋の名月 天空で餅つく兎に学ばねば
「色、人を迷わさず人自ら迷う」とは、色欲が人を迷わせるのではなく、人が自分で迷うのである、との意。ハニートラップには引っかかった方が憂き目にあう。よって、よくよく注意しなければなりません。旧暦8月15日は中国では中秋節。天空から兎が遠回しに警告を発している?
万策尽きた時にはさっさと【走為上】 撤退は恥ずかしくはない
「走為上」は、「三十六計逃げるに如かず」の語源となった言葉。何が何でも成功するぞという意気込みと、用意周到にして中国に進出。しかし、思惑通りに伸展せず万策尽きた時には、さっさと撤退するのも有り。
【巧詐は拙誠に如かず】 偽タクシーにびっくり くそ真面目も困るが
「巧詐は拙誠に如かず」とは韓非子にある言葉。巧みに表面を取り繕うようなやり方(巧詐)は、拙くても誠実なやり方(拙誠)には及ばない、と。その線引きは簡単ではありませんが、部下を持つリーダーとしては、拙くても誠実なやり方をベースとしたいものです。
【水の下きに就くがごとし】 奇を衒うことなく 坐りの良い序を
「水の下きに就くがごとし」とは、孟子の言葉で、水は低い方に流れるとの意。会社組織で、「序」を軽視すると、結果としては業績を拡大することは非常に困難になりかねません。実力と年齢など「序」に従った組織作りが、中国では特に求められます。