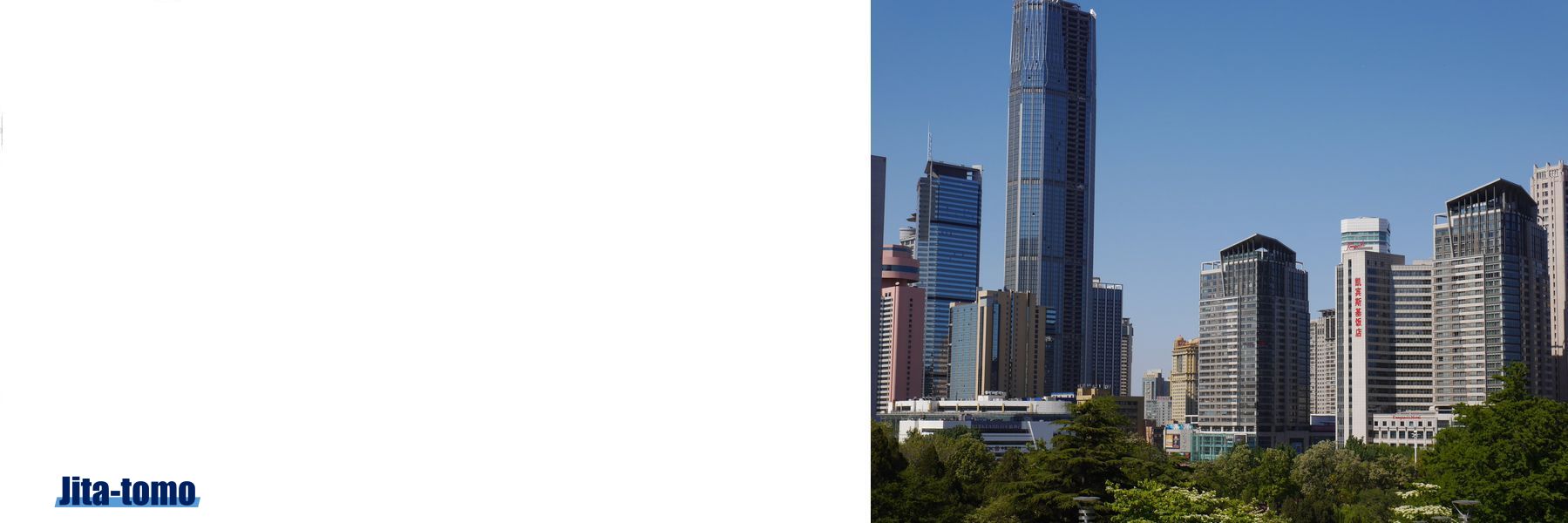【不懂装懂】の知ったかぶりが商機を取り逃がす 部下は信じるなとは
韓非子は「人主の患いは人を信じるに在り」という言葉を残しています。会社で言えばリーダーは部下を信じてはならないと。性悪説躍如としたこの言葉に少なからず抵抗感を持ちますが、実は中国では必須の考え方。なぜなら、社員の幸福、会社の発展がここに潜んでいるからです。
社員相手に【軽慮浅謀】の言動では自ら落し穴に堕ちるようなもの
「軽慮浅謀」とは、浅はかで軽々しい考えや計略のこと。会社のリーダーである立場の人が、社員に対してこんな対応をするということは、自らが落し穴にはまるようなもの。
できる社員が【善く游ぐ者は溺れ善く騎る者は堕つ】の罠に陥りがち どうする?
「善く游ぐ者は溺れ善く騎る者は堕つ」とは、自信があると、反って油断し思わぬ失敗をすることがある。よって、自信過剰になってはならない、との戒めの言葉。そのためには、相手を尊重しする姿勢、態度、つまり、謙譲の心を身に着けることです。
【人を恃(たの)むは自ら恃むに如かず】 当てにはできない帰属意識の薄い社員
「人を恃(たの)むは自ら恃むに如かず」とは、他人を当てにする事は愚かなことであるという韓非子にある言葉。
部下社員から、会社のために命を惜しまず頑張るぞ、なんてことを部下から言われたら嬉しいに違いありません。手を握り「頼むぞ!」と手を握りたくもなりますが…
このゲテモノを食え とは言わぬが【装模作様】では勝てぬぞ
「装模作様」とは、格好をつけて、もったいぶること。現地にどっぷり浸かって仕事をするのですから、何事にも、もったいぶっていては、成功を手にするのは難しい。「そんなゲテモノ、食えるか!」と言ってたのでは、身も蓋も無い。
生真面目とは別の【深謀遠慮】 此処での成功には老練さが無いと
「深謀遠慮」とは、深く考えを巡らし、遠い先のことをも考えること。そこには、老練とか老獪さが連想され、言葉の響きも、胡散臭いものを感じます。しかし、アウエーでの戦いにおいては、綺麗ごとを言っていたのでは、勝利するなど不可能に近いのです。
【人生の大病は只是一の傲の字】自分の傲慢さに気づき 賢と徳で心服を
「人生の大病は只是一の傲の字」とは王陽明の残した言葉。人生で最も害になるのは「傲」の一字である、との意。成功を勝ち取るためには、滲み出てくるほどの「人間的魅力」を身につける不断の努力をすることが何よりも大切。
清明節の焼紙銭 【哀哀たる父母】への尽きない感謝の思い
「孝は百行の首(はじめ)」とは、親孝行はあらゆる善行の中でその第一番目であるとの意。自分よりも年長者を重んじる中国社会にあって、自分の親に対する尊敬の念は特別です。苦労して自分を育ててくれた親の思いに感謝する気持ちが溢れていて感動します。
施策を巡らし【冥思苦索】 知恵を絞る総経理 その結果が思わぬ行動に…
「冥思苦索」は、思案を巡らし、知恵を絞ること。どのようなことであれ、目的を達成するのは容易ではありません。だからこそ、周囲の理解・協力を得て、諸問題に対応し、妥当な「解」を見出すために、必死に考えなければなりません。
現実的でない【以心伝心】 人頼みにせず下手でも自力で直接
「以心傳心(以心伝心)」は、もとは仏教用語で、言葉や文字を使わなくても、互いの気持ちが通じ合うことの例え。現実にはそんなマジックは期待できない。上手でなくてもかまわない、自分の口で中国語で話しかける。どんなにハイレベルの通訳が話すよりも思いはよく伝わる。