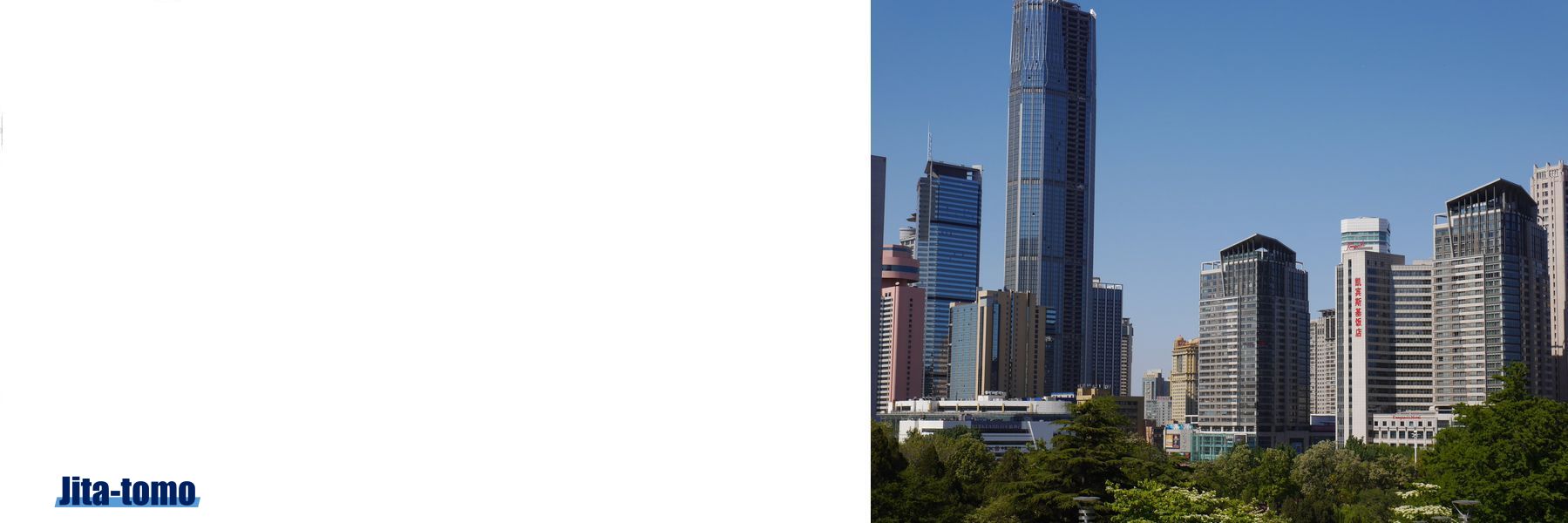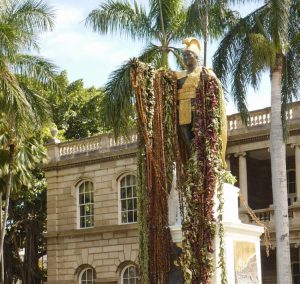【人の性は悪】というではないか 中国では性悪説が嵌る そして社員を守る
「人の性は悪、その善なるは偽なり」とは、人の本性は悪であり、それが善であることは、後になって身に着けた人為によるものである、との意。性悪説といえば、耳に心地よくはないが、これこそが、社員達を守り、ひいては自分をも守る事ができる考え方なのです。
【抜苗助長】 一生懸命なのだが とんでもない悲劇はこうして起きた
「抜苗助長」とは、功を焦って誤った方法をとると必ず失敗することを例えた言葉。責任者たるものは。その意図するところを理解し、自分の言動が、組織全体の清濁を決めることになる事を知らなければならない。
成功に繋がる【一葉知秋】を理解し実行できるデリカシーを持っているか
「一葉知秋」とは、一葉落ちて天下の秋を知る、との意。些細なことから物事の本質や成り行きを察知することを例えた言葉。デリカシーが無いことには、些細なことには反応することが難しい。中国での事業発展に欠かせないものは、スピード感と人間的ぬくもりのある思いやりです。
隔世の感がする変化 【夜郎自大】との謗りを受けないために
「夜郎自大」とは、自分の力量をわきまえず、尊大で高慢な態度で威張ること。総経理として派遣されてはいるが、それほど大した人間ではないのに、そんな態度では成功はおぼつかない。
【危うきこと朝露の若し】 平時に対策を講じる 成功には何より命が大切
「危うきこと朝露の若し」とは、日が出ると乾いて無くなる朝露のように、一刻の猶予もできない危険な状態にあること。その事を理解し、平常時においてこそ対策をしておかなければならない。
【先入の語を以て主と為す無かれ】 自らの不明を恥じる驚きの結果が
「先入の語を以て主と為す無かれ」とは、先入観や固定観念にとらわれることを戒めた言葉。人は、ややもすれば先入観を持ちがちであるが、これは時として危うさも一緒に持つことになる。
【千丈の堤も螻蟻の穴を以て潰ゆ】 小さな相手を見くびるという情けない行動
「千丈の堤も螻蟻の穴を以て潰ゆ」とは、些細な油断や不注意から思いもよらない大事を引き起こすとを例えた、韓非子の言葉。常に謙虚さと誠実さを持ち、たとえ小さな相手であったとしても侮らず、真摯な態度で臨むべきである。
【欲は縦(ほしいまま)にすべからず】 会社の権力者が 糸の切れた凧では…
「欲は縦(ほしいまま)にすべからず」とは、礼記にある言葉で、自分の欲だけを満たそうとしてはならない、との意。総経理(社長)には会社の権力が集中し、その気になれば、やりたい放題が可能。しかし、それでは巧くないのは明白。そこで必要なのは、自己規制。
【不拘一格】 自分の経験・習慣に拘るのもほどほどに 環境も習慣も違う
「不拘一格」とは、決まった形式にこだわらない、との意。自身の成功体験などを通して、こうあるべきだというような考えを持つのは理解できるが、それを環境の異なる中国で押し付けるのは失敗のもと。
【標新立異】感動の恩返しと思いきや… 主流の個人主義にどう対応する
「投桃报李」とは、人から受けた恩は忘れずにいて、お返しができるようになったらお返しをすること。そんな感動話には要注意。個人主義への対応がマネジメントのポイントのひとつ。