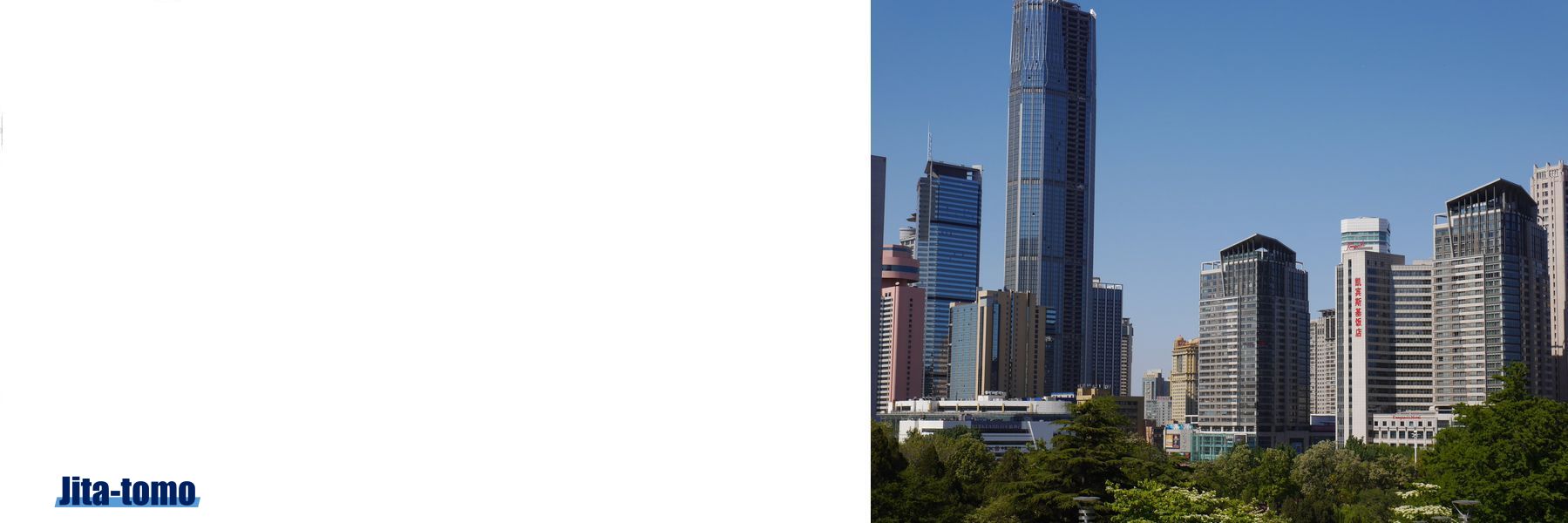【安くして危うきを忘れず】 またか!日中間の軋み 対応の極意は…
「安くして危うきを忘れず」とは、安泰な時にあっても危うさを忘れてはならない、との意。安逸に陥らず、常に緊張感を持ちたいものです。
【時に順じ而して動く】 中国で白酒ではなくワインのソーダ割りだと…
「時に順じ而して動く(順時而動)」とは、時勢や状況、機運に順応して行動する、との意。変化の激しい社会に於いては、このフレキシブルな考え方が大事であろう。
【百尺の竿頭】 昨日より今日 今日より明日という努力が成功の因
「百尺の竿頭、更に一歩を進む」とは、高い地位に達していても、留まることなく更に向上するよう努力することの例え。前進することを止めれば、敗退への始まりと…
【善悪の報いは影の形に随うが若し】だからこそ善にも悪にも対応しなければ…
「善悪の報いは影の形に随うが若し」とは、旧唐書にある言葉で、善事や悪事の報いは、物の影が形に沿って見られるように確実に現れる、との意。ならば、自分はどうあるべきか、が見えてくる。
【哭する人に対しては笑うこと勿れ】 人生の喜怒哀楽 大切な思いやりの心
「哭する人に対しては笑うこと勿れ」は、呻吟語にある言葉。他者の感情に寄り添い、思いやりのある行動を心がけることが重要である。困難な状況にある人々に対しては、配慮と共感が不可欠であるとの意。
【四時の序、功を成す者は去る】 やり方次第では自縄自縛に陥り勝ち抜けない
「四時の序、功を成す者は去る」とは、役目を終えた「春」は、その座を「夏」に譲るように、成功し役割を終えたら、表舞台から身を引くべきだ、との意。しかし、会社組織に在っては、「成功者」を、暫くは内部に留保した方が良いこともあると思うのだが…
【君の明らかなる所以の者は、兼聴すればなり】聞く耳を持つ でも鵜呑みは禁物
「君の明らかなる所以の者は、兼聴すればなり」とは、明君の明君たるゆえんは広く臣下の進言に耳を傾けることである、との意。権力を持つ立場であっても、聞く耳は持っていたいものです。
【大功を成す者は衆に謀らず】 責任をもって決断する勇気は有るか
「大功を成す者は衆に謀らず」とは、部下の意見など聞くべきを聞いたのなら、自ら決断する。大きな成功を収める人は群衆からのアドバイスを求めない、との言葉。
【己を推して人に及ぼす】 あんな上司は願い下げと言われるようでは…
「己を推して人に及ぼす(推己及人)」とは、他人の立場に立って自分のことのように考える、との意。これが、管理者として成功する第一歩ではなかろうか。
【小人は険を行いて以て幸を徼む】 これではアウエーでの成功は無理
「君子は易に居て以て命を俟ち、小人は険を行いて以て幸を徼む」とは、君子は無理のない所にとどまり、天命を待つ。小人は険しい行為によってあてにならない幸福を求める、との中庸にある言葉。